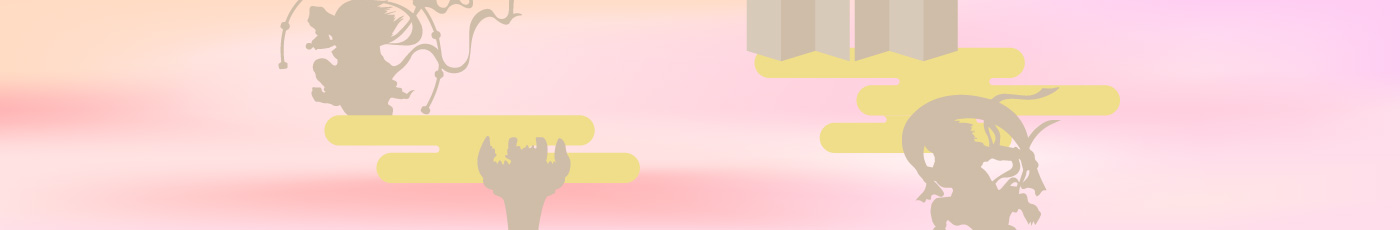六甲山と銅鐸を祭る人びと

海と人びとの歴史が作り出した街、神戸。古くは奈良時代から港が整備され始めたとされ、江戸時代の終わりごろにはいち早く諸外国との窓口として開かれた港町になりました。いまでも近代的な洋館のたたずまいを見て取ることができ、神戸と聞けば近代と現代が入り混じる港湾都市の風景を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
しかし、神戸にはもう一つ、山の街としての顔があります。傾斜地に広がる街区から北を仰ぎ見れば、急峻な六甲山麓がそびえたちます。そして、山並みから連なるこの六甲山南麓東部が、日本有数の銅鐸(どうたく)集中地域であることは意外に知られていないかもしれません。今回ご紹介したいのは、ここ神戸に生きた弥生時代の人びとと、その祈りの象徴たる銅鐸を紹介する展覧会です。

生田神社参道より六甲山を臨む
銅鐸は今から2000年ほど前の弥生時代に用いられた祭りのカネです。人びとが暮らすムラの繁栄を祈って鳴らされ、最終的には、ムラの外に埋納されることで知られています。今からおよそ60年前の1964年、ここ神戸の六甲山南麓の中腹で人びとを驚かせる大発見がありました。灘区桜ヶ丘町での銅鐸・銅戈(どうか)の発見です。精緻な幾何学文様と豊富な絵画で飾られた4・5号鐸をはじめ、さまざまな特徴をもつ14口の銅鐸と武器形の青銅祭器である銅戈7本が埋められていたのです。これらは発見から5年後には、地方自治体が所有する考古の文化財として、初めての国宝に指定されています。
現在、神戸市立博物館ではこの桜ヶ丘銅鐸を中心とした特別展「銅鐸とムラ─国宝 桜ヶ丘銅鐸をめぐる弥生の営み─」が開催中です。文化財活用センターは貸与促進事業の一環として本特別展に協力しており、東京国立博物館が所蔵する、神戸市出土の銅鐸2件が里帰りしています。
▷▷貸与促進事業とは

ここでは、この展覧会の様子と私のおすすめの楽しみ方をご紹介いたします。

博物館入口の様子
大きくカメラに収まらなかった神戸市立博物館の建物は、昭和10年(1935)竣工の国の登録有形文化財です。かつては横浜正金銀行神戸支店ビルだったそうです。

博物館内には桜ヶ丘銅鐸の絵画をあしらったステンドグラスも・・・・
本展覧会は、タイトルの通り前半ではさまざまな銅鐸を、後半ではムラの暮らしを紹介しています。
まず初めに、桜ヶ丘銅鐸の大量埋納といった側面に着眼し、島根県加茂岩倉(かもいわくら)遺跡や滋賀県大岩山(おおいわやま)遺跡といった代表的な青銅器埋納遺跡の銅鐸・銅戈が登場します。こちらはぜひ皆さんの目でご覧ください!
これに続くのが六甲山南麓東部出土の銅鐸、そして東京国立博物館よりお貸し出しいたしました兵庫県神戸市東灘区森北町出土銅鐸と兵庫県神戸市東灘区渦森台(うずもりだい)出土銅鐸です。所蔵先もそれぞれ異なる銅鐸が、一堂に会します。
 [左]外縁付鈕式銅鐸 弥生時代(中期) 兵庫県神戸市東灘区森北町出土
[左]外縁付鈕式銅鐸 弥生時代(中期) 兵庫県神戸市東灘区森北町出土
[右]扁平鈕式銅鐸 弥生時代(中期) 兵庫県神戸市東灘区渦森台出土 (左右とも東京国立博物館蔵)
また、本展覧会は銅鐸にまつわるコンテンツも充実。銅鐸の大きさやそのバリエーションを体感できるコーナーや、3Dで銅鐸をさまざまな角度から見ることができるコーナーがあります。

銅鐸背比べ

タッチパネルの簡単操作で、桜ヶ丘銅鐸を様々な角度から観察できます
そして後半は、銅鐸が埋められたころのムラの様子を紹介しています。桜ヶ丘銅鐸が埋められた、紀元前後の近畿地方一帯では、それまで発達してきた低地のムラは規模が小さくなっていき、対照的に山あいの高地にムラが出現します。神戸市域も高地にムラが確認できるようになる代表的な地域です。また、六甲山南麓東部では低地と高地のムラの両方の周辺に銅鐸が埋められたのも特色です。

銅鐸を伴う低地のムラ、北青木(きたおおぎ)遺跡出土の土器
なぜ低地と高地のそれぞれにムラがつくられるのか、そしてどうして六甲山南麓東部には銅鐸が集中しているのか。実はこの謎は、今なお多くの研究者の頭を悩ませています。六甲山南麓東部の周りの地域には、銅鐸が決して豊富にあるわけではありません。桜ヶ丘銅鐸・銅戈群をはじめ、なぜこの地に青銅祭器が集まってきたのか、そしてなぜその埋納地もこの山腹を選んだのか、未だに明らかになっていません。
現地に行けばわかるかもしれない・・・と気になった筆者は、今回お貸出しした銅鐸の出土地である神戸市東灘区渦森台を訪れてみました。バスにゆられること20分、渦森台は海沿いから山手へ続く造成団地の最も高いところに位置する住宅街で、ここより北側はより急峻な六甲山の山林になっていました。そして、振り返れば・・・眼下に街並みを一望でき、大阪湾まで見通せる大変眺望が良い場所でした。

渦森台からの眺望
「弥生時代の人びとは低地からも見通せる眺めの良い丘陵を選んだ結果、六甲山南麓の東側に銅鐸が集中した」と言いたいところですが、実はこれはあくまでも渦森台の場合。桜ヶ丘銅鐸をはじめ、銅鐸の埋納遺跡は当時の生活圏から見えにくい場所であることも多いのです。でも、やはり実際に行ってみることでしか得られない、標高の高さや眺望といった実感もありました。展覧会で銅鐸を見た後には、是非その出土地を訪れることもおすすめします!
以上、簡単ではありますが、本展覧会の様子とその見どころをほんの少しご紹介いたしました。神戸市立博物館は本展覧会の他にも常設展が充実。人が住み始めた旧石器時代から現代にいたるまで神戸の歴史を体感することができ、国宝 桜ヶ丘銅鐸・銅戈群をじっくり観察することができる専用の展示室もあります。

神戸市立博物館の常設展示。五色塚(ごしきづか)古墳が築造された当時の様子を再現したジオラマも!

国宝 桜ヶ丘銅鐸・銅戈の展示室(※特別展会場には桜ヶ丘銅鐸のうち3号鐸、11号鐸、4号銅戈を展示。その他残りは専用の展示室でご覧いただけます)
また、実際に銅鐸の音をひろがりを当時のように野外で聞いてみたい方は、神戸埋蔵文化財センター(神戸市西区)にもお立ち寄りください。神戸市内の文化財が数多く展示されているほか、併設の公園で桜ヶ丘銅鐸のレプリカを鳴らすことができます。

実は屋外で鳴らすことのできる銅鐸レプリカは非常に希少・・・筆者の一押しです!
特別展「銅鐸とムラ─国宝 桜ヶ丘銅鐸をめぐる弥生の営み─」は2025年8月31日(日)まで。ぜひ展覧会に足をお運びいただき、六甲山を眺めた人びとに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
銅鐸とムラ─国宝 桜ヶ丘銅鐸をめぐる弥生の営み─
会期 2025年7月5日(土)~2025年8月31日(日)
会場 神戸市立博物館(神戸市中央区京町24番地)
開館時間 9時30分〜17時30分(金曜と土曜は20時まで) ※展示室への入場は閉館の30分前まで
休館日 月曜日、7月22日(火)、8月12日(火) ※ただし、7月21日(月・祝日)・8月11日(月・祝日)は開館
入場料 一般1,500円(1,300円)、大学生750円(650円)、高校生以下無料
※本展観覧券にて同時開催特別展・コレクション展示室も入場いただけます
※( )内は20名以上の団体料金
※神戸市内在住で満65歳以上の方は、窓口にて証明書の提示により、当日一般料金の半額
※障害のある方は障害者手帳などの提示で無料
※大学生以下の方は、学生証・生徒手帳などをご提示ください
神戸市立博物館・公式サイト https://kobecitymuseum.jp/
神戸市立博物館・Instagram https://www.instagram.com/kobemuseum/
神戸市立博物館・facebook https://www.facebook.com/kobemuseum
神戸市立博物館・X https://x.com/kobemuseum
- posted by
- at
- 2025年07月29日 (火)